-
所長 挨拶
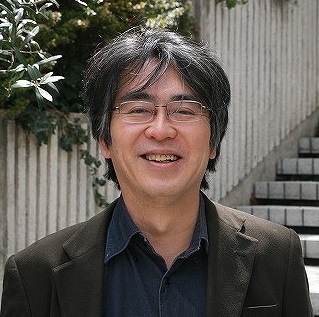 ヨーロッパの国々、たとえばドイツの地方を車や列車で旅すると、小麦畑のあいだに時々あらわれる村の集落の中心に、必ず教会が立っているのが印象に残ります。こうしたことは、あくまでヨーロッパの話で、日本ではまったく文化的背景が違うと以前は思っていましたが、ある時から決してそうではないと考えるようになりました。
ヨーロッパの国々、たとえばドイツの地方を車や列車で旅すると、小麦畑のあいだに時々あらわれる村の集落の中心に、必ず教会が立っているのが印象に残ります。こうしたことは、あくまでヨーロッパの話で、日本ではまったく文化的背景が違うと以前は思っていましたが、ある時から決してそうではないと考えるようになりました。
思えば、祭りや様々な年中行事からもわかるように、日本では地域やコミュニティの中心として神社やお寺がありました。はじめて知った時ずいぶん驚いたのですが、全国に存在する神社・お寺の数はそれぞれ約8万1千、約8万6千にのぼります。中学校の数は全国で約1万、あれほど多いと思われるコンビニの数も5万弱なので、これは大変な数と言えます。
これほどの数の“宗教的空間”が全国にくまなく分布している国はむしろ珍しく、戦後、急速な都市への人口移動と経済成長へのまい進の中で、そうした存在は人々の意識の中心から単に一時的にはずれていっただけなのです。
加えて興味深いのは、日本の神社やお寺と「自然」との結びつきです。「鎮守の森」という言葉が象徴するように、そこでは森や木々などの自然が不可欠なものとなっており、自然の中に、物質的なものあるいは有と無を超えた何かを見出してきた生命観・宇宙観をよく示しています。そしてこれは、決して日本のみに限らず、地球上の様々な地域におけるもっとも基層にある自然信仰や世界観と通底していると思われます。
さて興味深いことに近年、地域コミュニティへの関心が高まる中で、こうした神社やお寺という、高度成長期に人々の関心の中心からはずれていった場所を地域の貴重な“社会資源”として再評価し、それを子育てや高齢者ケアなどの福祉的活動や、環境学習等の場として活用するという例が現れてきています。 本研究所は、以上のような関心を踏まえ、自然やスピリチュアリティ(物質的なものを超えた精神的価値)と一体になったローカル・コミュニティの拠点としての「鎮守の森」を軸として、自然エネルギーやケア、地域再生との関わりなど、現代におけるその新たな意義と可能性を、具体的な活動とともに探求していくことを目的とするものです。
鎮守の森コミュニティ研究所 所長
広井良典
-
研究員紹介
研究員の経歴等は研究員紹介のページをご参照ください
| 名前 | 所属・活動 | |
|---|---|---|
| 所長 | 広井 良典 | 京都大学人と社会の未来研究院教授 |
| 副所長 | 宮下 佳廣 | 千葉大学法政経学部福祉環境研究センター特別研究員 |
| 特別研究員 | 松尾 寿裕 | 全国小水力利用推進協議会理事・運営委員 |
| 特別研究員 | 藤本 頼生 | 國學院大學神道文化学部准教授 |
| 特別研究員 | 新井 君美 | 秩父神社権禰宜 |
| 特別研究員 | 馬上 丈司 | 千葉エコ・エネルギー㈱ 代表取締役 |
| 特別研究員 | 松尾 貴臣 | 音楽活動家 |
| 特別研究員 | 本間 裕康 | 福山福祉専門学校「東洋医学介護論」講師 東洋セラピストカレッジ学院長 |
| 特別研究員 | 倉橋 陽子 | 森林セラピーガイド 林業女子@大阪代表 山の上のヨーガ教室主宰 |
| 特別研究員 | 大原 学 | 一般社団法人マツリズム 代表理事 |
| 特別研究員 | 片桐 尉晶(保昭) | (有)風土計画舎 代表取締役 |
| 特別研究員 | 清水 彰 | 京都錦市場商店街振興組合 事務長 |
| 研究員 | 小池 哲司 | ㈱ダイナックス都市環境研究所 主任研究員 |
| 研究員 | 中村 安里 | 京都大学総合生存学館博士課程 |
| 研究員 | 島 碧斗 | 東京大学工学部化学生命工学科 |
| 連携研究員 | 中村 京子 | 音楽療法コーディネーター |
| 研究員 | 長谷川 南 | 千葉大学大学院人文社会科学研究科 |
